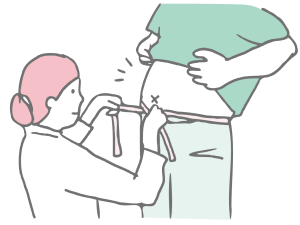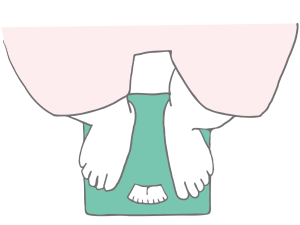美味しいイワシを食べよう!
2025年 6月 20日 金曜日
イワシを普段から召し上がりますか?
イワシというと一年中流通している魚ですが、もしかすると食べる機会は多くないかもしれません。
私も頻繁には食べませんが、この時期に出回る「入梅イワシ」は大好きです。

「入梅イワシ」は、梅雨に入る時期に水揚げされるマイワシのことで、特に千葉県銚子沖をはじめとした関東の太平洋沖のマイワシは、この時期が1年の中で最も脂乗りが良いそうです。
では、今の時期に美味しいイワシには、どんな栄養があるのでしょうか・・・?
- オメガ3脂肪酸
「青魚と言えばオメガ3」とすっかりおなじみの栄養素ですが、イワシも例に漏れずオメガ3脂肪酸であるDHAやEPAが豊富に含まれています。
DHAやEPAは血液をサラサラにし、動脈硬化や心疾患の予防に役立つほか、抗炎症作用もあります。
また、DHAは脳の働きを活性化にも関わるとされています。
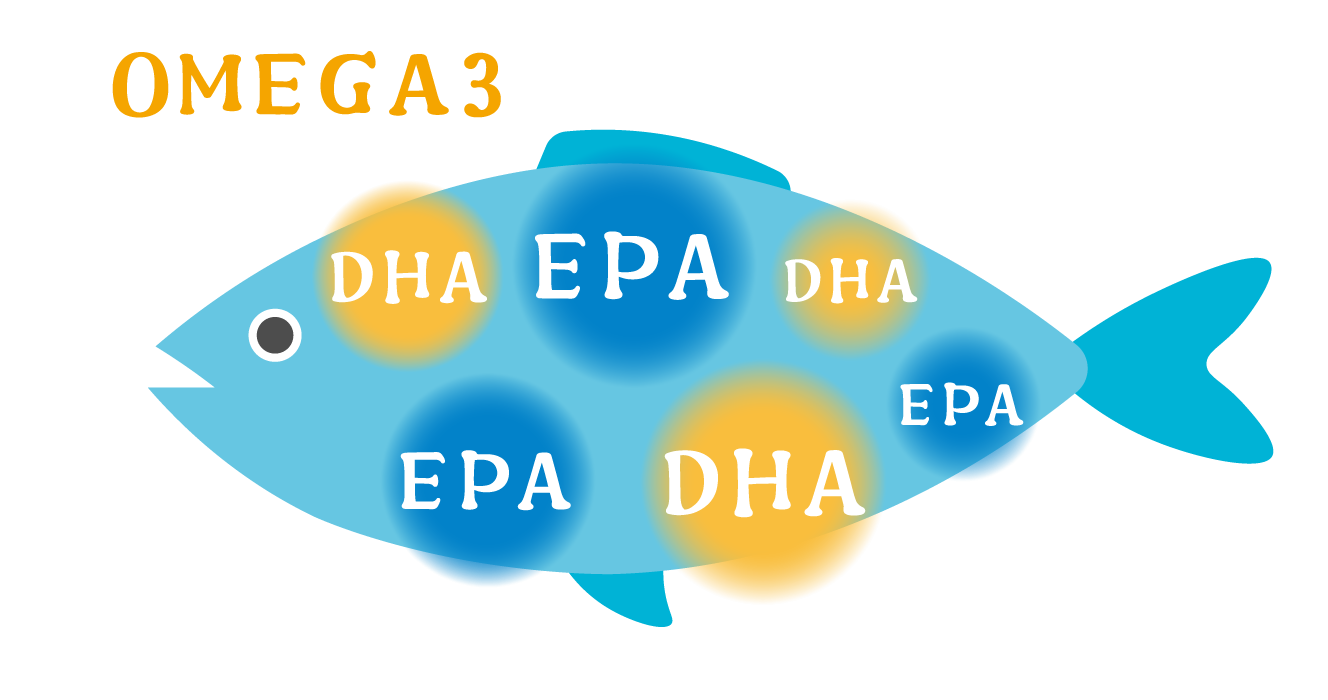
- カルシウム
イワシは骨ごと食べられる魚なので、カルシウムを効率よく摂取できます。カルシウムは骨や歯を強くするだけでなく、筋肉や神経の働きをサポートする役割もあります。特に成長期のお子様や骨粗しょう症が気になる方におすすめです。
- ビタミンD
イワシにはビタミンDも豊富に含まれています。ビタミンDはカルシウムの吸収を助けます。また、免疫力を高める働きもあります。ビタミンDは紫外線を浴びることで皮膚から合成されますが、日中あまり外に出ない方やしっかりと紫外線対策をしている方には特に食べ物から積極的に摂取したい栄養素です。
脂がのって美味しいイワシ、食べ方はお刺身など生で食べることが一番おすすめです!

EPA・DHAは時間が経つにつれ、また調理工程を経ることで酸化しやすく、徐々に失われていきます。新鮮なうちに召し上がることが美味しく、栄養をより無駄なく摂取できるコツです。
酸化を防ぐためにビタミンCやビタミンEが役立つので、柑橘を添えたり、お酒を飲みながらゆっくり味わいたい時にはカルパッチョやマリネが良いかもしれません。
さて、突然ですが6/4~6/10は日本歯科医師会等が提唱する
「歯と口の健康週間」でした。
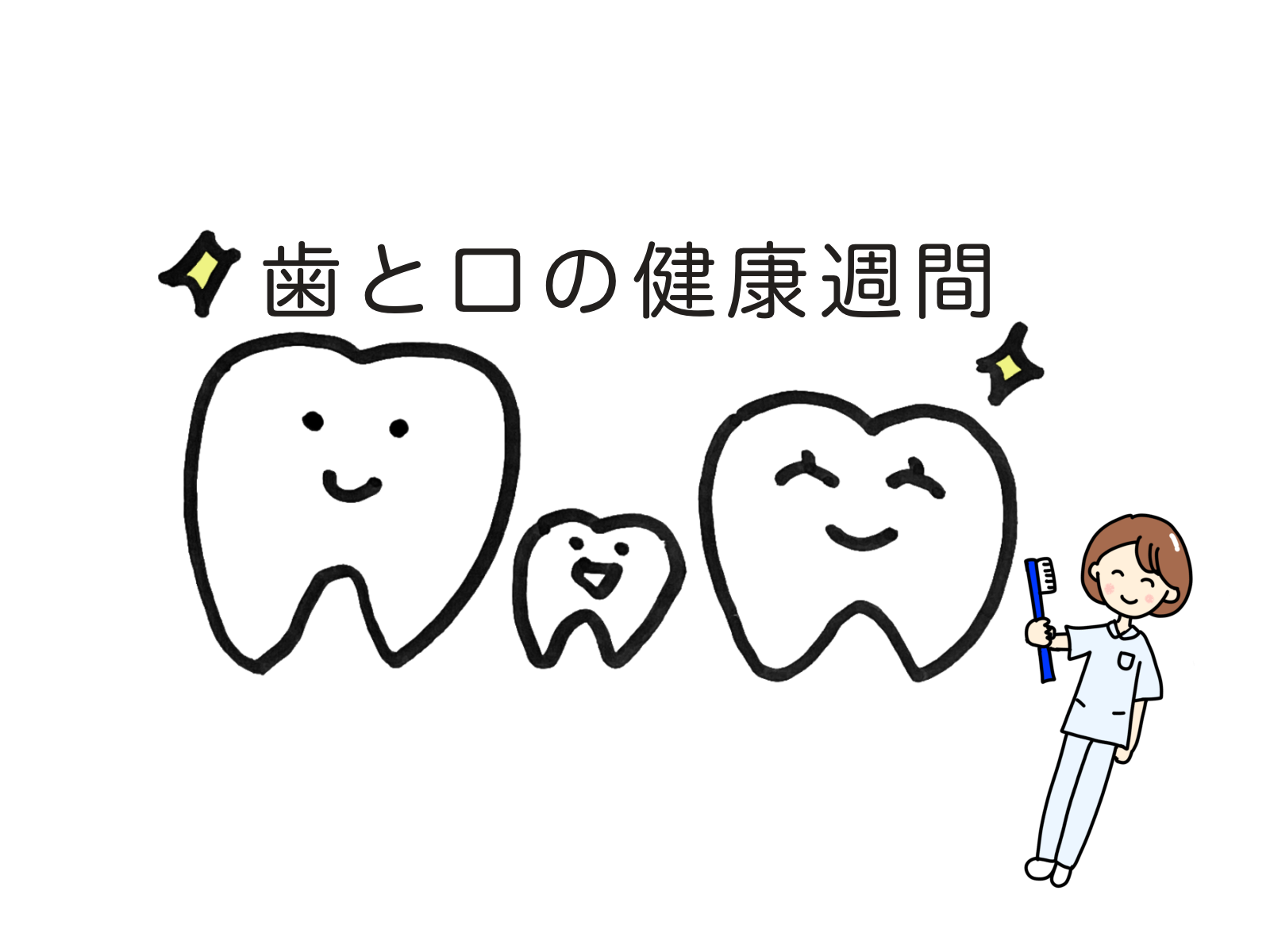
カルシウムやビタミンDは歯の健康には言わずもがな、オメガ3脂肪酸においても「歯周病患者は歯周病がない健康な方と比べて血清オメガ3脂肪酸の濃度が低い」という報告があるようです。
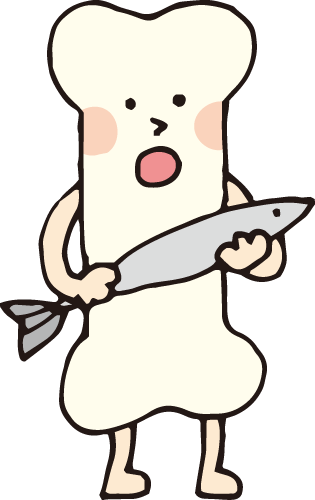
特に美味しくて栄養豊富なこの時期のイワシを食べて、食べ物からも歯の健康を意識してみませんか?
EPファーマラインでは新しい仲間を募集しています!詳細はこちら▼

Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類