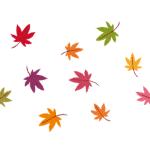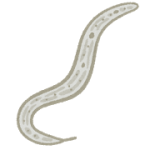赤カブ
2017年 11月 28日 火曜日

あっという間に今年も残すところ1ヶ月となりました。
12月に入ると大掃除や年賀状、おせちの準備等、
やらなければいけないことがたくさんありますね。
毎年、計画的に進めようと思うのですが、
結局、年末年始の休みに入ってからバタバタと片付けるのが
恒例になっています。
今年こそは余裕を持って終わらせたいと思う今日この頃・・・。
さて、今回は赤カブについてです。

カブにはよく売られている小さめのものから、千枚漬けに使われる
聖護院かぶのような大きいもの等、様々な品種があります。
その中で、表面の皮や果肉が赤いものが赤カブです。
赤カブは10~12月頃に旬を迎えます。
赤カブの赤みはアントシアニンによるものですです。
アントシアニンはポリフェノールの一種で、赤~紫色を呈します。
ブルーベリーやいちご、なす、紫キャベツ、黒豆等に含まれています。
ポリフェノールには抗酸化作用があります。
身体の中の活性酸素が増加すると、細胞を酸化させ老化を引き起こしたり、
動脈硬化や癌の原因にもなります。
ポリフェノールはこの活性酸素の生成を抑制します。
老化防止や動脈硬化等の予防にポリフェノールの摂取が推奨されるのは、
抗酸化作用によるものです。
それでは赤カブのレシピを1つご紹介します。
■赤カブ漬け
・赤カブ 500g
・食塩 20g
・砂糖 50g
・酢 100mL
①赤カブは皮を剥かずに食べやすい大きさに切る。
②塩を振り、よく混ぜた後、1時間位放置する。
③水気を軽く切りながらジッパー付きの袋に入れる。
④袋に砂糖と酢を入れ、冷蔵庫で3~4日漬ければ出来上がり。


赤カブのアントシアニンにより、かぶ全体が綺麗に赤く染まります。
日持ちもするため、おせち料理にもお勧めです。
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類
 季節はすっかり秋めいてきました。
季節はすっかり秋めいてきました。