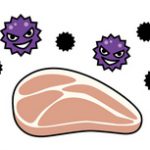熱中症
2017年 7月 26日 水曜日
先 週、関東では梅雨明けを迎えました。
週、関東では梅雨明けを迎えました。
梅雨が明けると、暑さも一気に増す気がしますね。
この時期に注意が必要なのが熱中症です。
熱中症の発症時期は、
7月中旬~8月上旬にピークを迎えます。
今年5月~7月中旬に全国で熱中症により
救急搬送されたのは19,914人です。
昨年同時期の16,509人を大幅に上回っています。
熱中症というと、炎天下で起こるとイメージをする方も多いと思いますが、
いちばん多い発生場所は家の中なんです。
救急搬送された方の1/3以上が家の中で熱中症になっています。
そして全体の半数が高齢者です。
高齢者は年齢とともに体内水分量や体温の調節機能、
熱に対する感受性が低下するため、熱中症にもなりやすくなります。
近年、炎天下での熱中症は減少傾向ですが、
高齢者の日常生活における熱中症は増加傾向にあります。
熱中症は、体内での熱の産出と熱の放散バランスが崩れて、
体温が著しく上昇した状態です。
脱水状態を伴っていることがほとんどです。
暑い中にいる時、もしくは、いた後の体調不良は、熱中症の可能性があります。
熱中症は重症度によってⅠ度~Ⅲ度に分かれています。
Ⅰ度:めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、こむら返り
Ⅱ度:頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下
Ⅲ度:意識障害、痙攣発作、肝・腎機能障害、高体温
それでは、熱中症にならないためには、どうすればいいでしょうか?
暑さ対策としては、
■エアコンや扇風機を活用する。
■炎天下での外出時は、帽子や日傘を利用する。
■保冷剤や冷たいタオルで体を冷やす。
などがあります。
そして、何より大切なことは水分、塩分補給です。
水だけを補給すると、体液が薄まります。
体液の濃度を保つために利尿が起こり、脱水が進行します。
また、水だけを多量に補給すると血中のナトリウム濃度が低くなり水中毒となります。
水中毒では、死に至ることもあります。
熱中症対策には、水だけでなくて塩分も必要です。
水分補給には、食塩濃度が0.1~0.2%程度のスポーツドリンクや経口補水液がお勧めです。
熱中症になりやすい状況の場合には、20~30分ごとにカップ1~2杯を目安に摂取しましょう。
暑いと食欲も無くなりますが、食事量が少なくなると、食事からの塩分摂取量が減ってしまいます。
熱中症対策には、しっかり食事を摂ることも大切です。
暑さ対策と十分な水分、塩分補給で熱中症を防ぎましょう。
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類


 残念ながらウエルシュ菌は
残念ながらウエルシュ菌は