ハロウィン
2016年 10月 25日 火曜日
 秋も深まり、コートが手放せない季節になりましたね。
秋も深まり、コートが手放せない季節になりましたね。
10月のイベントと言えばハロウィンですね。
ちょっと前まであまり縁がないものと思っていましたが、
昨年、友達とハロウィンパーティーに参加してみました。
包帯を顔中に巻いたり、映画やアニメのキャラクター、著名人等、
様々な仮装で盛り上がりました。
近年は、至る所でハロウィンイベントが行われていますね。
.
元々、ハロウィンは秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す儀式として行われていました。
名前の由来には諸説ありますが、Hallowとは聖人のことであり、
カトリックで11月1日は聖人の日とされています。
10月31日はHallows eveと言われており、それが訛り、Halloweenとなったそうです。
今日の日本では、宗教的な意味合いは薄れ、1つのイベントとして楽しまれています。
ハロウィンでは、ジャック・オー・ランタンが飾られますよね。
かぼちゃをくり抜いて作るランタンですが、当初はカブが使用されていました。
..
アイルランドに伝わる昔話ですが・・・
悪事を働き、天国にも地獄にも行けなかったジャックは、
道に転がっていたカブをくり抜き、その中に火の塊を入れて、
ランタン代わりに使ったそうです。
これがジャック・オー・ランタンの由来です。
その後、アメリカでは生産量の多かったかぼちゃが
使用されるようになり、かぼちゃが主流になりました。
かぼちゃは、西洋かぼちゃ、日本かぼちゃ、ペポカボチャの3種類に分類されます。
ジャック・オー・ランタンに使用される
オレンジ色のかぼちゃは、ペポカボチャです。
ペポカボチャは食用には適しておらず、観賞用にされています。
食用として流通しているものは、
西洋かぼちゃと日本かぼちゃです。
それでは、日本で最も流通しているかぼちゃはどちらでしょうか。
正解は、西洋かぼちゃです。
西洋かぼちゃはホクホクしていて甘みがあり、栗かぼちゃとも言われるものです。
えびす、雪化粧、みやこ等の品種があり、スーパーでもよく見かけるかぼちゃです。
それに対して、日本かぼちゃは水っぽく、煮崩れしやすい特徴があります。
 さて、バターナッツというかぼちゃをご存知でしょうか。
さて、バターナッツというかぼちゃをご存知でしょうか。
名前から想像すると西洋かぼちゃのようですが、
バターナッツは日本かぼちゃの一種です。
近年、注目度が高まっていて、時々、店頭に並んでいることもあります。
名前の通り、濃厚でバターのようにねっとりしていて、
ナッツに似た風味があります。
ポタージュやサラダにお勧めです。
ハロウィンまであと少し!
仮装やかぼちゃ料理でハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか。
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類

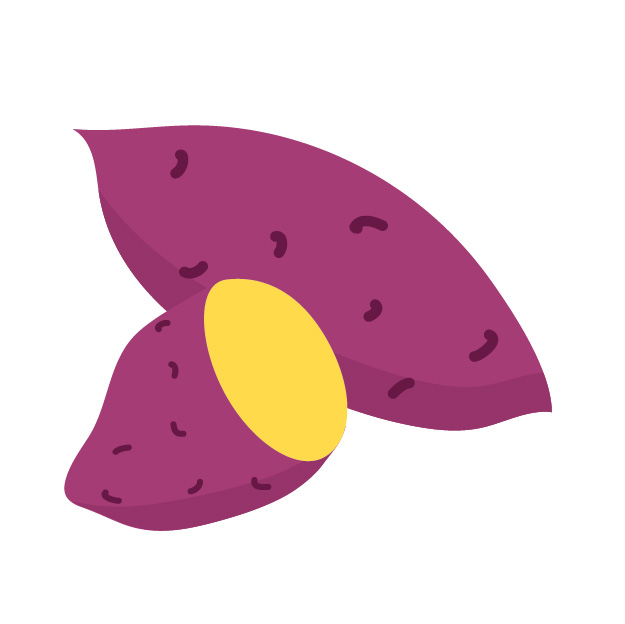
 、
、


