土用の丑の日
2016年 7月 28日 木曜日
やっと関東地方でも梅雨明けをしましたね。これから、ますます暑い日が続きそうですね。
みなさん、体調など崩されていませんか?
夏のスタミナ食として「うなぎ」を連想する方もいるのではないでしょうか。
今回は、「うなぎ」についてのお話です。
この時期、うなぎと聞くと、土用の丑の日を連想する方も多いのではないでしょうか。
ちなみに、今年の土用の丑の日は、7月30日です。
◆土用の丑の日
土用と聞くと、夏のイメージですが、実は1年を通してあるんです。
土用とは、立春、立夏、立秋、立冬前の約18日間のことを指します。
7月20日から8月7日頃までが、夏の土用の期間になります。
なぜ丑の日というのでしょうか?
十二支というのをご存知でしょうか?子丑寅卯・・・と続くものです。
丑の日とは、十二支の中の『丑』のことです。
つまり、土用の期間のうち丑の日に当てはまる日が、『土用の丑の日』ということになります。
◆うなぎの栄養 
うなぎと聞くと、栄養豊富なイメージを持つ方も多いと思います。
具体的には、どのような栄養素が豊富なのでしょうか?
うなぎには、ビタミンAやビタミンB1、ビタミンD、ビタミンEが豊富に含まれています。そのほか、カルシウム、カリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など体に不可欠な栄養素が多く含まれています。また、脂質の中でもEPAやDHAが豊富に含まれています。
各栄養素の働きを簡単に説明すると、
ビタミンA(レチノール)は、皮膚や粘膜を正常に保ち、免疫力を高める働きがあります。
レチノールは、妊娠中も必要な栄養素ですが、妊娠初期の妊婦さんは注意が必要です。
体外に排出されにくい特性があるため、摂取量に注意が必要です。妊娠初期の妊婦さんが、レチノールを過剰摂取すると胎児が奇形・先天異常などの障害を持った状態で生まれてくる可能性が高まるといわれています。
毎日、大量に食べなければ問題ないのですが、妊娠初期の方には注意が必要なことを踏まえてください。
ビタミンB1は、生きる上で必要不可欠なエネルギーを作る働きと、神経機能や脳を正常に保つ働きがあります。
ビタミンDは、小腸や腎臓でカルシウムとリンの吸収を促進し、血液中のカルシウム濃度を保って丈夫な骨をつくる働きがあります。
ビタミンEは、からだの酸化を防ぐ「抗酸化作用」があります。動脈硬化などの生活習慣病を予防することが期待されています。
DHAやEPAは、体内では作ることのできない脂肪酸です。
DHAは脳の働きを活発にし、EPAは血管を丈夫にすると言われています。
◆うなぎの蒲焼
うなぎの蒲焼は、関東風と関西風で違いがあります。
関東風と関西風の蒲焼は「さばき方」と「焼き方」が異なります。
関東では、うなぎを背開きにして白焼きした後、蒸して再び焼くため、ふわっと柔らかいのが特徴です。タレは関西に比べてあっさりしています。
関西では、小ぶりのうなぎを選んで腹から開いて蒸さずに焼くため、脂の乗ったパリッとした香ばしさを楽しめます。タレは、うなぎの脂に負けないようにトロッと濃くて甘いです。また、関西風は頭が付いていることが多いのも特徴です。
◆開き方が異なる理由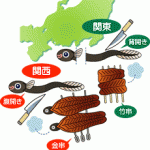
≪背開き≫
関東では、武士などの文化が強いため、腹を切るということは「切腹」を意味してしまい、縁起が悪いとされてきました。その為、背開きをするようになりました。また、うなぎの腹の部分には美味しさの脂が乗っているのでそれを逃さない調理法でもあります。
≪腹開き≫
関西方面では、商業や商人の文化が強く、お互い腹を割って話をするという事から腹開きがされるようになったという説があります。
今年の夏は、例年よりも暑くなる予報が出ています。
水分補給も忘れずに、スタミナをつけて暑い夏を乗りきりましょう!
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類
 梅雨空が続いていますね。
梅雨空が続いていますね。











