サプリメントの選び方
2011年 11月 18日 金曜日
こんにちは。せぇです![]()
寒くなってきましたね。
最近の私のお気に入りはホット豆乳です![]()
もともと大豆製品全般があまり得意ではないのですが、
数年ぶりに飲んだ豆乳がなぜかとてもおいしく感じ、すっかりマイブームです。
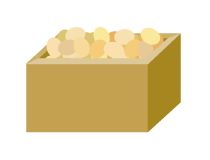 大豆製品はといえばイソフラボン
大豆製品はといえばイソフラボン
イソフラボンは、「植物エストロゲン」とも呼ばれ、
更年期障害等への有効性が示唆されています。
サプリメントも販売されていますが、
イソフラボンをサプリメントで摂取する場合には注意が必要。
食品に含まれている成分だからサプリメントで摂っても問題ない・・・
というわけではないんです。
イソフラボンサプリメントには、乳がん発症や再発のリスクを高める等、
有害性を示唆するという報告もあります。
サプリメントはお手軽に摂取できますが、その分過剰摂取につながりやすいという
反面があります。
今回は![]() サプリメント選びのポイント
サプリメント選びのポイント![]() をご紹介します。
をご紹介します。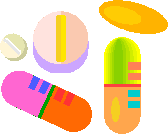
最近の新聞には、毎日のようにサプリメントの広告が
掲載されています。
中にはサプリメントで病気が治ると思わせるようなものも
氾濫しているため、しっかりとサプリメントを見分けることが
大切ですね![]()
■サプリメントは薬ではない!
サプリメントで病気は治りません。
また、いくらサプリメントを飲んでいても、食事が整っていなければ意味がありません。
サプリメントは、食事で不足している分を補うという考えで利用しましょう。
■そのサプリメントが本当に必要か?
例えば・・・毎日納豆を食べている人はイソフラボンのサプリメントは必要ないですよね。
また、「必須アミノ酸」のサプリメントも売られていますが、肉や魚をしっかり食べている人には
不要と考えられます。
■エビデンス(科学的根拠)は?
「○○に効く」と言われていても、本当にそれが確かな情報とは限りません。
国立健康・栄養研究所のホームページには、健康食品の有効性・安全性に関する情報が
掲載されています。
一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか?
■含まれている量は?
ビタミンCは100gあたり12mg以上含まれている場合に、「ビタミンC含有」という表示ができます。
このように、ビタミン等には「含有」という表示ができる基準値が決まっています。
しかし、DHAやイソフラボン等のように基準値が決まっていない栄養成分もあります。
DHA含有と書いてあるのに、実際には数mgしか含まれていないという場合もあります。
含有量をしっかり確認することも重要です。
■安全性は?
誤って医薬品の成分が混入していたり、それによって健康被害が現れる場合もあります。
サプリメントを利用する場合には、信頼できるメーカーを選ぶということも大切ですね。
メディカルラインでもサプリメントに関するお問合せ対応を行っています。
NR(栄養情報担当者)として正しい情報を提供できるよう努めていきたいです。
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 日記



 こんにちは、Koharuです。 暑い日が続いていますが、夏バテなどされていませんでしょうか。
こんにちは、Koharuです。 暑い日が続いていますが、夏バテなどされていませんでしょうか。


