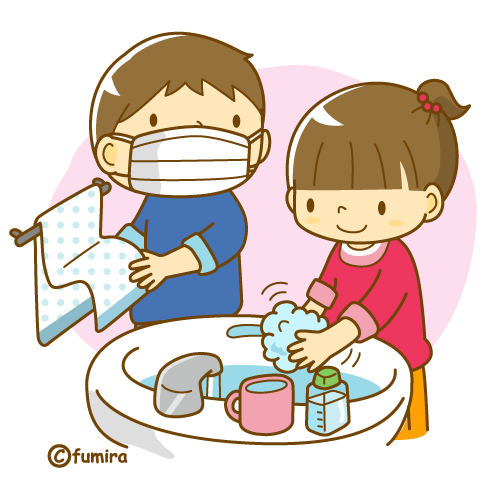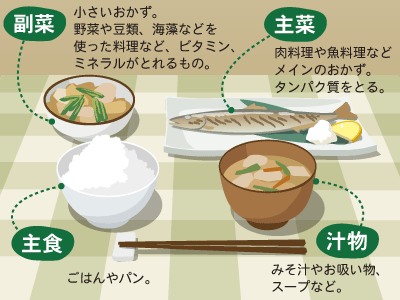糖分を含む飲み物に注意!
2020年 5月 7日 木曜日
5月に入り、暖かい日が増えてきましたね 😀
これから水分補給をする機会が多くなると思います。
本日は「糖分を含む飲み物に注意!」をテーマにお話させて頂きます。
皆さんは普段からどのような飲み物で水分補給を行っていますか?
水、お茶、炭酸飲料、ジュースなど様々だと思いますが、
糖分を含む以下の飲み物の飲み過ぎは、肥満や糖尿病を招く恐れがあるため注意が必要です。
●炭酸飲料
水に炭酸ガスを入れて果汁・乳・砂糖・甘味料・香料などを加えた飲料です。
炭酸飲料で代表的なサイダーは、ペットボトル500mlで『角砂糖約15個分』の糖分が含まれています。
最近では、糖分が含まれない炭酸水も増えていますので、糖分が気になる方にお勧めです。

●果汁入り・濃縮還元ジュース
果物のビタミンやミネラルを含むため体によさそうなイメージですが、果糖が多く含まれていてること、また、果物より食物繊維が少なく、液体のため糖分の吸収が早く、血糖値が急激に上がりやすい飲み物でもあります。
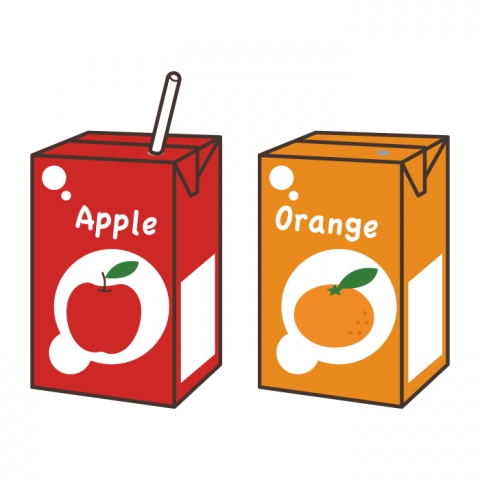
●スポーツ飲料
塩分と糖分の濃度や浸透圧を調整することによって、水分を速やかに体内に吸収することができる飲料です。
そのため、夏場や喉の渇きを感じた時の水分補給には適していますが、ブドウ糖や果糖が多く含まれているため、 飲み過ぎには注意が必要です。

●「ゼロ・低カロリー」や「ノンシュガー」飲料
これらの飲料は、栄養成分表示において規定があり、「0」でなくても基準値を満たしていれば「ゼロ・低カロリー」や「ノンシュガー」と表示することができるため、必ずしもカロリー「0」kcal・砂糖「0」gとは限りません。
「ゼロ・低カロリー」や「ノンシュガー」と表示されているからといって安心して 飲み過ぎてしまうと、血糖値が上がったり、体重増加の原因になります。
参考:厚生労働省 eヘルスネット
●「ペットボトル症候群」に注意!
「ペットボトル症候群」とは、炭酸飲料や清涼飲料水の多飲により、糖分の摂り過ぎで高血糖を招く状態です。
血糖値が上昇すると喉が渇くため、さらに飲みたくなるという悪循環に陥り、糖尿病にかかる危険性もあります。


●水分補給はお水、お茶を中心に
このように「糖分を含む飲み物」は、日常的に飲み過ぎると肥満や糖尿病を招くリスクが高まります。
お水、お茶など、カロリーや糖分がない飲み物を中心に、その時の状況に合わせて水分補給を行い、1日の糖分摂取量が過剰にならないよう気を付けましょう 😉

Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類