リコピン
2019年 8月 13日 火曜日
暑い季節になりましたね!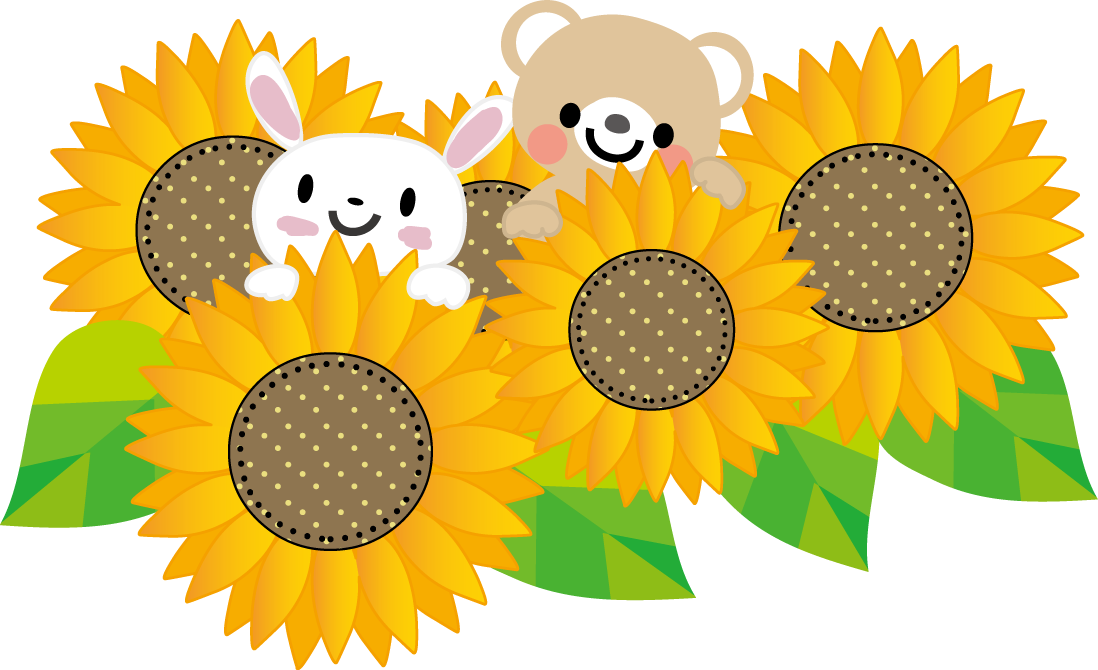
体調管理を心がけて、暑い夏を乗り切りましょう! 😎
今月はリコピンのお話をしたいと思います。
私事ですが、大学でリコピンについて研究をしていました。
夏野菜のトマトやスイカに豊富に含まれていま す。
す。
リコピンとは・・・
カロテノイド(動植物に含まれる赤や黄色、オレンジ色の色素)のひとつです。
ビタミンと同じように人の体内では作り出すことができないので、食べ物から摂るしかありません。
抗酸化作用が高く、ビタミンEの100倍以上!
健康や美容の面からも様々な効能が期待されています!!
リコピンの働きをご紹介します! 🙂
血流を改善し生活習慣病を予防
抗酸化作用は悪玉(LDL)コレステロールの酸化を抑制し、血流を改善します。
体の酸化は老化を促進し、病気の原因になります。
酸化の原因である活性酸素を除去する作用を持つリコピンはこれらを予防します。
美肌効果
活性酸素を除去する作用は、美しい肌の生成と保持に深く関わりがあります。
紫外線によっても増加する活性酸素は、シミやくすみの原因であるメラニン色素の生成を促進する作用を持つため、抗酸化作用によって、肌の透肌明感を維持する効果も期待されています。
肥満を予防する効果
リコピンの血流改善作用は、臓器や細胞の働きを活発化させて代謝を上げ、
脂肪などが蓄積されにくい体をつくると期待されています。
また、抗酸化作用によって、脂肪細胞の増加を防ぐことができると考えられています。
目の健康の維持
活性酸素を原因とする視覚機能の低下に有効であるといわれています。
また、加齢によって起こる白内障や黄斑変性症などの視覚障害の予防や改善にはルテインが
効果的ですが、リコピンもルテインとの相互作用で効果を発揮することが明らかとなっています。
ここからはリコピンを含むトマトについてです。
旬の8月には2月の約3倍のリコピンが含まれるというデータがあります!
☆おいしいトマトの選び方☆
①真っ赤に熟しているもの
②ヘタやガクが濃い緑色で、ピンとしていて枯れていないもの
③全体の色が均一で皮に張りのあるもの
④持ってみてずっしりと重たいもの
⑤お尻の部分の放射状の線がはっきりしているもの
☆効率的に摂る方法☆
加熱調理をする
油に溶けやすい性質のため、油と一緒に食べることで吸収率がアップ!
また、にんにくや玉ねぎといったユリ科野菜を油で加熱調理することで、体内に吸収されやすい構造への変化が促進されます。
<トマトソース・シチュー・スープ>
加工品を利用
リコピンだけでなく、トマトの成分が濃縮されています。![]()
また、手軽に使えて便利です。
<トマトケチャップ・ホールトマト・トマトピューレ>
朝のトマトジュースが効果的
朝が1番リコピンの吸収が良いことが明らかになっています。
また、牛乳と組み合わせると効率よく摂ることができ、
カルシウムも補うことができます!
<牛乳をかけたシリアル+トマトジュース>
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類



 ぜひ、鰻を食べて、夏バテしないようにしましょう!!
ぜひ、鰻を食べて、夏バテしないようにしましょう!! 6月になり梅雨を迎え、本格的に夏が近づいています。
6月になり梅雨を迎え、本格的に夏が近づいています。
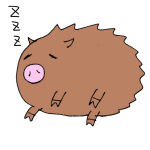 自分に合ったよい眠り方の方法を見つけることで快適な睡眠をとりたいですね!
自分に合ったよい眠り方の方法を見つけることで快適な睡眠をとりたいですね!
