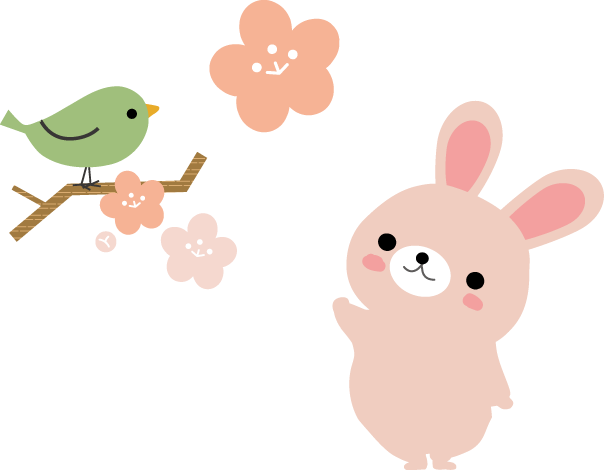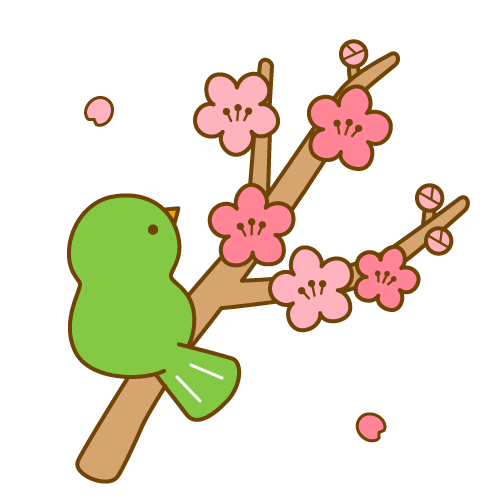桃の節句♪
2012年 3月 2日 金曜日
こんにちは。エイです。
ひな祭りは、もともと古代中国の春に水辺で行われていた厄除けの習慣で、それが日本へ伝わり、3月3日の女の子の節句、雛人形を飾り女の子の健やかな成長と幸せを願う、ひな祭りとなったそうです。
ひな祭りの行事食といえば…菱餅、ひなあられ、ちらし寿司、はまぐりの潮汁などなど…いろいろな食事がありますね。その中から、今回はひなあられとはまぐりについて、お話ししたいと思います。
ひなあられは、昔、ひな人形を持って野山や海辺へ出かける「ひなの国見せ」という風習があり、その際に春のごちそうと一緒に、菱餅を砕いて作ったひなあられを持って行ったのが始まりと言われています。
色は桃色、白、緑の3色が主流で、桃色(赤)には生命・魔よけ、白には雪の大地・子孫繁栄・長寿、緑には木々の芽吹き・厄除け・健やかな成長の意味があり、自然の力を授かり健やかな子に育ってほしいという願いが込められています。
…実はこのひなあられ、関東と関西で違いがあるのはご存知ですか?
関東のひなあられは、米粒大で小さく、米を爆(は)ぜて作った“ポン菓子”を砂糖などで味付けしたもので甘く、関西のひなあられは、直径1センチ程度で大きく、餅からできており、しょう油や塩味などでいわゆる“あられ”なんです。
どちらが元祖なのか?についてはいろいろな説があるそうですが、菱餅を砕いて炒ったのが始まりとされていることなどから、関西風が元祖という説が有力のようです。
今は、関東でもピーナッツや大豆を甘くコーティングしたものや米粒大よりも大きな形をしたものが多くありますし、関西ではマヨネーズ味(!)やチョコレート味などのいろいろな味があるそうです。
…ちなみに、東海や北陸では両方を売っている場合が多く、関東風・関西風の垣根はどんどん低くなっているそうです。関東のスーパーでもしょうゆ・塩味のひなあられが並ぶ日も近いかもしれませんね。
●はまぐり
二枚貝のはまぐりは、対の貝殻しか絶対に合わないことから、何事にも相性の良い結婚相手と結ばれ、仲睦まじく過ごせるようにと願いをこめて、桃の節句に食べられるようになった、と言われています。
ちなみに、結婚式で縁起物として出されるのも同じ理由からで、その際は1つの貝に身を二つ入れるのが習わしとなっています。
はまぐりは、カルシウム、鉄、タウリン、亜鉛、ビタミンB12など日本人に不足しがちな栄養素が豊富な食材です。
カルシウムは体内で骨や歯を丈夫にし、細胞の情報伝達を助ける働きがあり、鉄分やビタミンB12は鉄欠乏性貧血に効果があります。タウリンはコレステロールを下げル働きや、疲労回復、肝機能強化の効果があります。
カロテンをほとんど含んでいないので、調理の際は、カロテンが豊富な三つ葉などと一緒に調理するのがおすすめ、貧血予防のためにはビタミンCを含む食品と一緒にとるのがおすすめです。
3月3日は、春を無事に迎えられたことを喜び、これからも皆が元気で過ごせるようにと願う日でもあります。
女の子を主役にするもよし! みんなで春を寿いでもよし!
ひなあられやはまぐりの料理、ちらし寿司など、みなさんもこの日にふさわしい食べ物や色を楽しみ、素敵に過ごしてみてはいかがでしょうか♪
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類