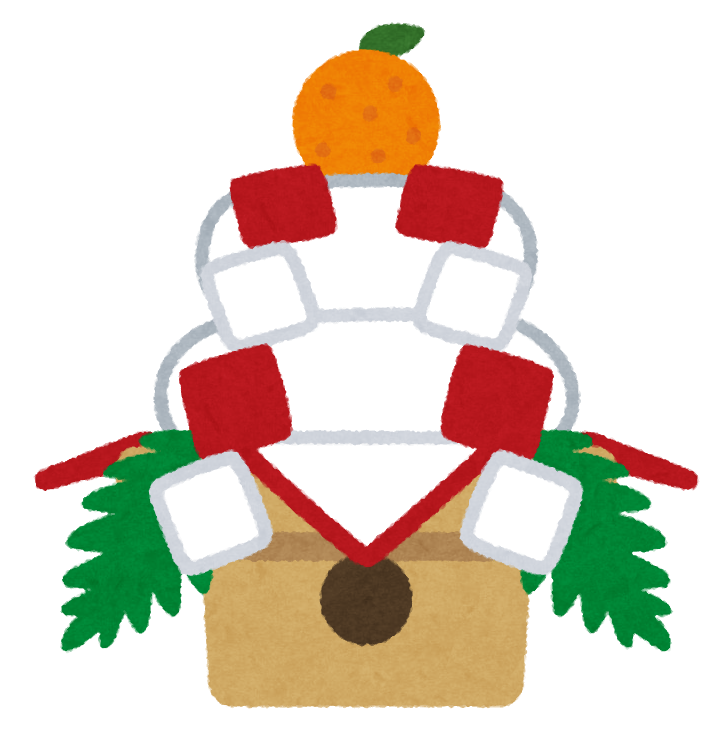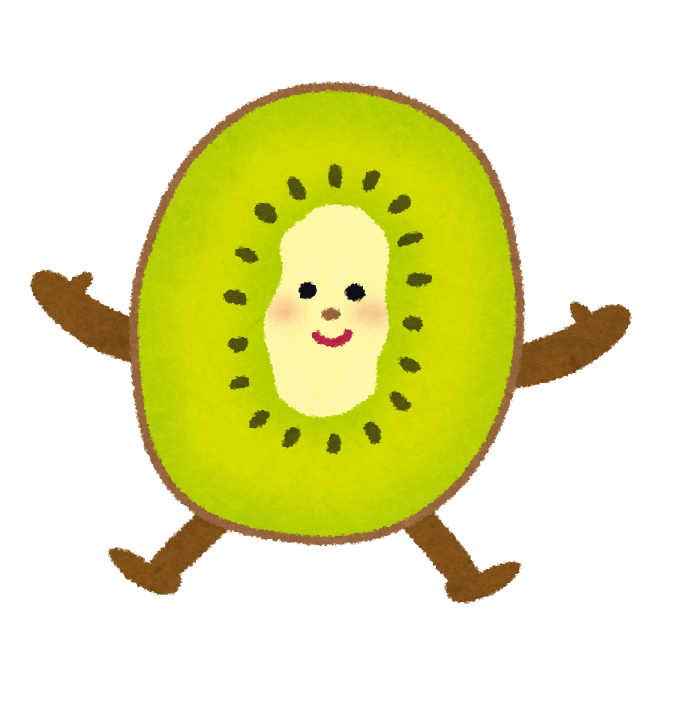お料理のススメ
2023年 2月 10日 金曜日
毎日寒い日が続きますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
寒い日は1歩も外に出ない!という方も多いのではないかと思います。
私も、休日はおうちでぬくぬくと過ごすことが多いのですが なんとなくモヤモヤする、気分転換できないかな~と感じることも増えてきました。
おうちでできる気分転換といえば 音楽を聞く、掃除をする、模様替えをする、軽い運動をする、など いろいろな方法があると思います。
自分にいちばん合う方法を探すうち、たどり着いたのは「料理」。
私は決して器用ではなく、どちらかというと大雑把な性格ですが、 料理をすると頭の中が整理され、スッキリすることに気づきました。
野菜を切ったり色よく焼いたりと、調理に集中することで余計なことを考えずに済み リラックスできているのだと感じます。
料理には様々なメリットがあることが分かっています。
●脳トレになる
「今日は何を作ろう?」「どんな食材がどのくらい必要?」 「どこに買い物に行けば効率的?」など、献立を立てる時点で頭を使います。
さらに、「お湯を沸かしている間に野菜を切っておこう」 「お肉の調理をする前に、生野菜サラダを作ったほうが良いな」など 調理工程の組み立てにも頭を使います。
●五感が刺激される
料理により味覚はもちろん、嗅覚や触覚などの感覚が刺激されます。
食材を包丁で切ったりトングで盛り付けたりと手を動かすため、 身体が不自由な方のリハビリに、料理が取り入れられるケースも あります。 小さなお子さんにとっては、五感が刺激されることで表現力や想像力が 豊かになることが期待できます。
●達成感を味わえる
料理をすることで「美味しいものが食べられる♪」というご褒美を得られます。 また「1つの料理を自分の力で完成させた!」と達成感も得られます。 これらが脳の刺激となってポジティブな感情に繋がります。 (先日、給食で食べた懐かしのカレーを再現でき、興奮しました。笑)
最近我が家では、食材を家まで届けてくれるサービスを使い始め、 仕事帰りにスーパーに寄る必要が無くなったことも、料理のハードルを下げてくれました。
料理をするようになってから食器にも興味が沸いてきて 生活の質がグッと上がった気がしています。
気分転換方法にお悩みの方は 一度お料理にトライしてみてはいかがでしょうか。
Posted by mlblog02.
カテゴリー: 未分類
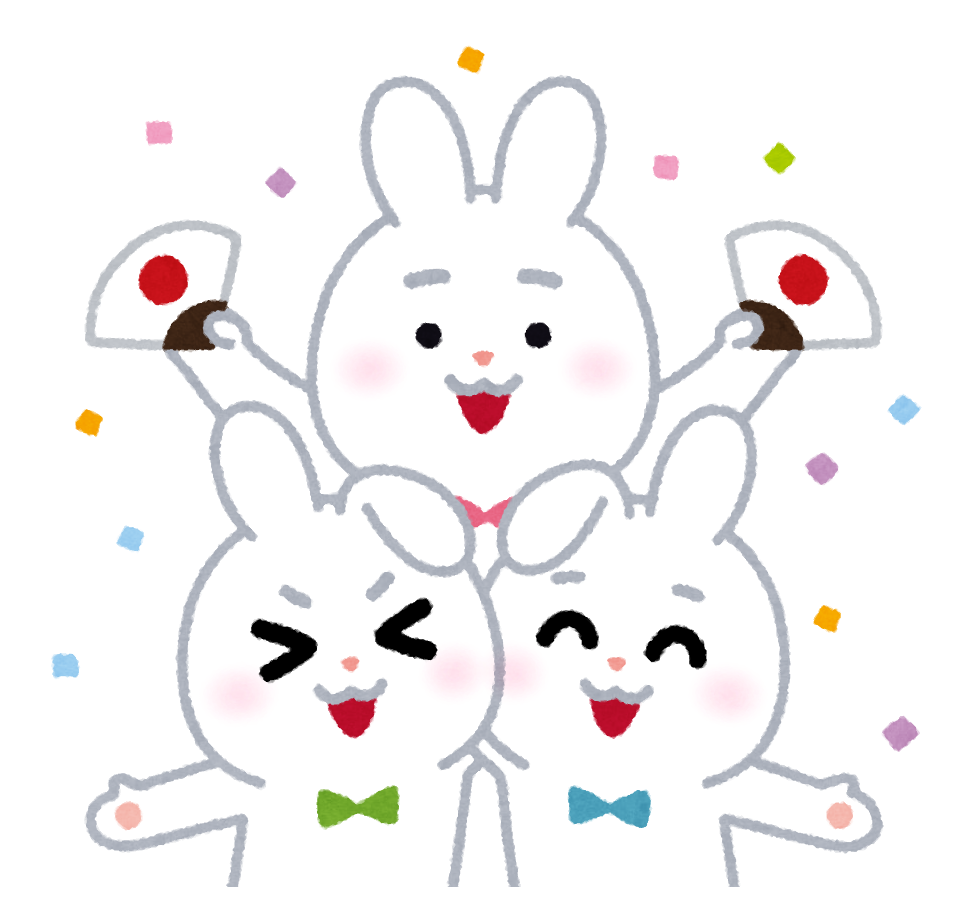 あけまして
あけまして